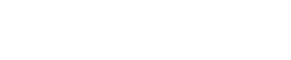PDFはこちら
【埋め立て強行辺野古移設問題 猿田佐世国際弁護士 核心”対案”】(サンデー毎日 12/30)
安倍政権は12月14日、辺野古沿岸部への土砂投入を開始した。移設反対の民意を無視し、民主主義のルールを踏みにじる暴挙である。今こそ野党は、辺野古新吉建設以外の道を探るべきではないか。米国との独自外交を展開してきた国際弁護士・猿田佐世氏に、基地問題の根本的な転換法を聞く。
◆ ◆ ◆
前号では、井手英策慶大教授の「増税世直し論」を紹介した。
行き詰まりつつあるアベノミクス、安倍晋三政権の主軸経済政策に対し、その成長至上主義路線への根源的批判に基づいた包括的対案を示したつもりである。野党各党におかれては、アベノミクス後の日本経済を展望するたたき台として是非参考にしていただきたい。
野党にはもう1つ仕事がある。現政権が「唯一の選択肢」とする米海兵隊普天間飛行場の辺野古移設(新基地建設)計画への対案提示である。というのも現政権のやり口が常軌を逸しているからだ。9月30日の沖縄知事選で移設反対の民意が圧倒的多数で示されてまだ3ヶ月経たない中で、玉城デニー新知事との対話もそこそこに埋め立てを強行した。民主主義国家としての体をなしていない。
なぜ政権が急ぐのか。来年2月の移設の可否を問う県民投票結果を恐れた所業だ。埋め立てを既成事実化で県民をあきらめさせ、米国にはいい顔をしようという腹が透けてみる。安部1強の中で、暴挙を重ねても押し切れる、とタカをくくっているのかもしれない。
かつて、橋本龍太郎、小渕恵三政権時代には、同じ保守政権でも、あの沖縄戦で本土の犠牲になった人々への贖罪意識や思い入れがあった。沖縄に過剰な基地負担を強いていることを政治の責任と感じる健全なバランス感覚があった。それに比べて、安倍、菅義偉官房長官ラインの鉄面皮、歴史忘却ぶりはどうだろうか。梶山静六、野中広務といった戦争世代の政治家が存命ならこの民意黙殺の愚挙をどう論難しただろう。
それはそれとして、今こそ野党の出番である、と言いたい。辺野古新基地建設しか道がないのか、を改めて徹底検証してほしい。現実的で実現可能な代替案(対案)を構築、国会論戦を通じもう1つの選択肢として高め上げてほしい。
3つ理由がある。1つは日米安保体制を正常化するためである。前々号で柳澤協二元内閣官房副長官補が指摘したように、特定機密保護法制定、集団的自衛権行使容認、米国兵器の買い付け増大などが物語る、現政権の過度な対米従属・軍事一体化路線をただすためである。日本の民意、国益をも反映した正常な関係を取り戻さないと、安保体制そのものが危殆に瀕する。
2つに、すでに有力な代替案があるからだ。民間シンクタンク「新外交イニシアティブ(ND)」(猿田佐世代表)が2017年2月に発表した「海兵隊新ローテ―ション案」がそれだ。
3つに、野党にしか期待できないからである。立憲民主党が8月に新基地反対を鮮明にした。対案作りの責めを負ったことになる。鳩山由紀夫政権の沖縄に寄り添う姿勢を取り戻し、あの時なぜ対案作りに失敗したか再検証すべき時だ。
まずは「新外交イニシアティブ(ND)」の紹介だ。沖縄問題を中心に外務省を窓口にした外交には反映されてこなかった日本の民意、声を、直接各国政府、議会、メディアに届けるため13年8月に設立された組織だ。15年には、米国防権限法案にあった「辺野古が唯一の選択肢」との条文を米議会への働きかけで取り除かせた実績を持つ。
「新ローテ案」は、12年に米軍再編の見直しが行われ、沖縄駐留の海兵隊の実戦部隊の大半がグアムなどに移駐、沖縄には司令部機能と、人道支援・災害救助を目的にローテーション(巡回)配備される2000人の海兵遠征隊しか残らなくなることを受け、立案された。骨格は、①その海兵遠征隊の拠点を沖縄から米本国に移す一方、日本政府は巡回移送を迅速化する高速輸送船を提供(借上げで年間11億円、新造500億円)、在沖海兵隊駐留経費の施設整備費(30億円)も現行のまま負担する、②同遠征隊がアジアで実施する人道支援・災害救助活動の訓練には自衛隊、中国軍も参加している実態を踏まえ、沖縄に連絡調整センターを設置し、残された海兵隊の司令部が各国代表と共同訓練の連絡調整に当たるーーというものだ。
米軍は直接巡回先に行けばいい
その論理はこうだ。そもそも米軍再編後に沖縄に残るとされる2000人の部隊では大規模紛争には全く対応できない。また、北朝鮮との紛争、尖閣諸島を巡る中国との争いでも、最初に投入されるのは海兵隊ではなく空軍・海軍である。さらに、その2000人の部隊は、現在、年間6~8カ月東南アジアなどを訓練で回り、沖縄にはいない。即ち、日本の安全保障の観点からみて、辺野古に基地を造る必要はなく、今の海兵隊のミッションは変わらず遂行可能という訳である。
兆円単位ともいわれる巨額な税金を投入し環境をも破壊する新基地建設の必要性がなくなるだけではない。戦中戦後にわたり多大な犠牲を払って来た沖縄が、中国を含むアジア安保を議論するソフトパワーの発信地となる。日本政府にとっても日米安保の目的であるアジアの平和と安全に貢献でき、海兵隊も負担が軽減される。抑止力の観点からも問題はない、と柳澤氏ら外交、安保、沖縄の専門家が3年がかりで練り上げた。
私には合理的、戦略的で、きちんとした理念にもとづいた案に見えるが、どうだろうか。猿田代表にも聞いた。
「海兵遠征隊は米国から6カ月単位で巡回し、マリアナ、フィリピン、韓国、タイなどアジア地域を回って、また米国に戻る、というローテーション配備で、沖縄立ち寄りは休養と訓練が目的です。であるならば、米本土から直接巡回先に行ったらどうですか、2000人に過ぎない巡回部隊のために新基地が必要ですか、ということです」
「米本土からだと移送に時間がかかるとの懸念には高速輸送船の提供で応えたい。災害救助に間に合わないということであれば、真っ先に自衛隊が飛んで手伝う。共同活動しようということだ。中国軍を巻き込むのはアジア安保のネットワーク作りという観点からも意義がある」
この案に対する米側反応は?
「ドラフト段階で米国の識者にも見てもらいました。17年2月に東京、沖縄で公表し、7月にはワシントンで英語版を元にシンポをやり、米議会要路にも配りました」
国防総省の担当者は?
「案を出す前と出した後での反応が異なった。作成前に、海兵隊の任務についてもっと細かく分析すべきだ、と言われたので、提言書を作成して持って行ったのですが『もっと大きく全体を見なければ』と言われた。それを聞いて、ああ、軍隊の配置は政治の意志さえあればどうにでもなるということかと痛感しました。どうにか見直そう、という時の政権、政治の意志があるかどうかです。沖縄の声を聞け、と言えば、この『新ローテ案』でもいいし、無視してもいいというなら今の新基地案強行のままです」
アーミテージ元国務副長官らジャパンハンドは?
「アーミテージ氏に直接説明したことはありません。ただ、彼の基本スタンスは、別に辺野古である必要はない、日本政府がそう言っているからそうするのだ、というものです」
日本側の反応は?
「外務、防衛両省にはオフレコベースで話していますが、『唯一の選択肢』のスタンスを変えません。国会議員を通じ質問主意書で政府見解も聞きましたが、私たちからみると質問からずれた回答もあり、沖縄に新基地を建設する説得的な理由は一切返ってきません」
外務省経由以外の対米パイプ
猿田氏にはこの辺野古移設問題で忘れられない原点がある。
9年前、猿田氏がワシントンで米議会への働きかけを始めた頃のことである。時の鳩山政権の「最低でも県外」という声がなぜ米政権中枢に届かないのかと疑問を感じ、米下院外交委員会のアジア太平洋小委員長と面談した。
「小委員長から『沖縄の人口は何人ですか。2000人くらいですか』と聞かれて驚きました。ただ、それが米国の実態だった。米国議会でもこの問題を知っている人はほとんどいない。話しているうちに、米国が一枚岩で日本に基地を押し付けているとのイメージは正確ではないこと、外務省や知日派を通じて聞く『これぞ米国の声』が相当歪んでいることがわかった。要は日米外交が国務、国防両省の日本担当者やそれを取り囲む一部の人たちの細くて強固なパイプだけで成立しており、それ以外の人たちはそれなりのポジションにいる議員でも関わることはない、そういう構造があった」
この経験から猿田氏は外務省経由以外の対米パイプ作りを独自に進め、日本から来る国会議員たちにさまざまな人脈を紹介してきた。玉城デニー氏の訪米には衆院議員時代に2度同行、枝野幸男立憲民主党代表の本年9月の訪米も日程作成を担当し、バーニー・サンダース上院議員らとの会談にも同席した。故・翁長雄志前知事にはワシントンに県直轄の出先事務所を置くよう提案し実現させた。そういったキャリアがあるだけに、今回の「新ローテ案」には政治の意志さえ伴えば実現可能との自信を抱いている。
そこで、この埋め立て強行だ。どう対抗すべきか?
「非常に残念だし、怒るべきことだが、今回の埋め立てのエリア自体は護岸で囲まれている部分だけで、全体計画からすればまだわずか、と聞いています。命が失われる海洋生物にとってもまだ一部です。ここで立ち止まっては土砂投入という既成事実をもとに沖縄の諦観を誘う政権の思うつぼです。まだまだ引き返せるという認識を日本国民、沖縄県民に広げることが大切。そのためにぜひメディアも協力してください」
猿田氏からはメディアに対しても注文がついた。
ここでせっかくの機会だから沖縄問題についてのメディアの役割を考えてみたい。1つは、このように行き詰った国策への対案を具体的に提示し、国会や世論に選択肢を広げた議論を促すことであろう。もう1つは、沖縄問題の原点である沖縄戦、日米軍民の死者数20万人、沖縄県民の4人に1人が亡くなったともいわれるあの惨劇を風化させず、その記憶と記録を頑なに継承することではなかろうか。
その後者の視点からまとめられた著作を紹介したい。
「魂(マブイ)の新聞」「『沖縄戦新聞』 沖縄戦の記憶と継承ジャーナリズム」(琉球新報社 18年12月)である。
著者は藤原健・毎日新聞大阪本社元編集局長である。新聞社を辞めてから沖縄大学大学院に入り直し、沖縄・東アジア地域研究を専攻、2年間琉球新報、沖縄タイムスに代表される沖縄ジャーナリズムについて研究を重ねて来た。その人となりについてはこの欄でも一回紹介した。新著はその修士論文に加筆したものだ。
「沖縄戦新聞」は琉球新報が戦後60年の節目である04年7月から05年9月まで延べ14回に連載した特集紙面で、若い記者たちが60年前に遡り、当時の報道を検証するとともに、新事実、証言を使い、言論統制の戦時下では伝えられなかった沖縄戦の全体像を現在の視点で再報道したもので、05年の新聞協会賞を受賞した。
藤原氏に言わせると、「『沖縄戦新聞』は新聞でありながら、その枠を超えようとした不思議な新聞であった。住民目線に依拠し沖縄戦を再現したが、同時に戦争を煽り、戦争を食い止めることができなかった当時の新聞、記者に対し深い反省を込めた『社告』の掲載を続けた。高校生みたいな真面目な新聞作りだ。。本土の新聞を含めて、そういう新聞を作ったことはなかった」となる。
「戦争のためにペンを執らない」
戦後生まれの記者たちに、なぜこれだけの新聞作りができたのか。その答えを出そうと、藤原氏は戦中、戦後にわたる両紙の歴史を振り返ると同時に、両紙の記事を、特に社会面の記事を読み込み、担当記者16人にもインタビューした。その結果、「沖縄の記者として」「長期にわたり」「住民の視点で」「未来への継承」を意識してきた両紙の思想が「沖縄戦新聞」に貫流し結実していたこと、記者たちが取材を通じ「二度と戦争のためにペンを執らない」という覚悟と決意を新たに獲得していく過程も浮き彫りになったという。
「僕は新聞記者の役割は、1つに戦争に加担しない、戦争を阻止すべくジャーナリズムの力を発揮すること。2つ目に権力を監視、局面によっては対峙すること。3つ目は弱い者の立場に立った新聞作りをすることだと思っている」
「戦争を体験した語り部が社会から引退していくと、新聞記者が継承者としてそれを担わざるを得なくなる。それを『継承ジャーナリズム』と言うと、私たちはそんなたいしたことをしているわけではない、と彼らは言う。ただ、こういうことをきちんと評価することが日本のジャーナリズム全体の底上げにつながる、と思う」
執筆中に胃がんで倒れ、現在も抗がん剤を使う療養中の身。全身ジャーナリストみたいな人物である。
猿田氏のリベラル現実主義とでもいうべき対案力、藤原氏の年季の入った記者魂。「沖縄」を考える時に不可欠な資質ではないだろうか。
※2018年12月30日事務局追記:
「沖縄県知事訪米仕掛け人」とありますが、新外交イニシアティブ(ND)は玉城デニー沖縄県知事の2018年10月の訪米は担当しておりません。