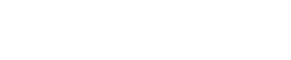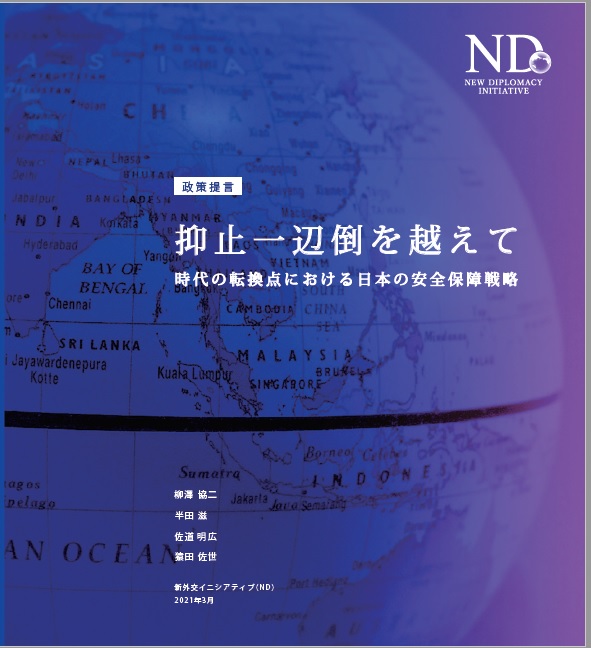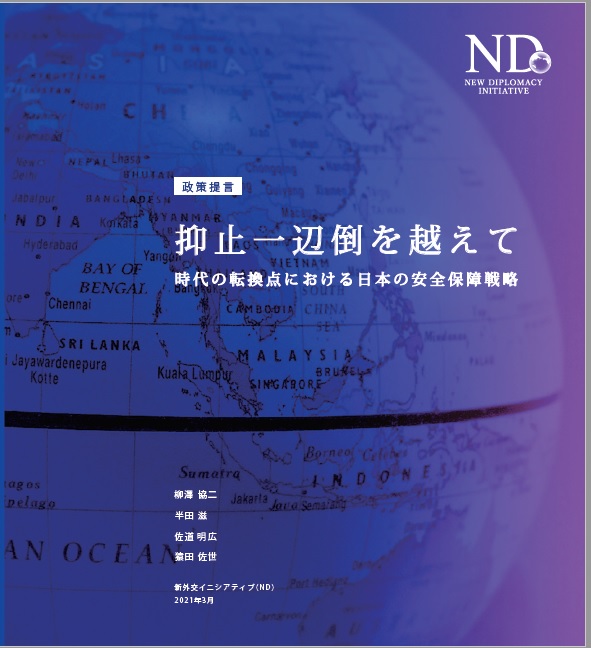PDF版はこちら
序論
冒頭に今回の提言の前提となる私たちの考え方から述べておきたい。
まず、安全保障という概念についてである。
そもそも安全保障とは、総合的なものであり、国家の存立にかかわるすべての課題について考えられるべきものである。食料や資源・エネルギーなど、国民生活に不可欠な物資の安定的確保や、地震や火山噴火などの自然災害への対応・復旧なども安全保障にかかわる課題である。新型コロナウイルス感染が世界規模で拡大し、人々の生活に決定的影響を与えている現在、これへの対応も極めて重要な安全保障の課題である。
すなわち安全保障とは、国家存立の在り方にかかわる問題である。無論、安全保障政策の中で軍事は重要な位置を占めているが、軍事がすべてではない。しかしながら現在の日本においては、安全保障の議論が軍事のみに偏っていることに私たちは懸念を抱いている。現在の軍事の議論においては、各国が開発・装備する軍備のカタログデータ的情報が独り歩きし、軍事バランス論や対抗戦術ばかりが安全保障論として議論されてはいないだろうか。安全保障を語る人々が、まるでかつての参謀本部員・軍令部員であるかのように議論しているとすら感じられる。
本来、戦術論レベルの議論に先んじて必要なのは、日本の現在の状況を客観的に評価・分析しながら、国際情勢の動向を見据えたうえで国家のありようについて考えた、広い視点に基づく戦略論的議論である。しかし、現在、その議論が不在であることを、私たちは強く懸念している。
次に、個別具体的な情勢に触れる前に、より大きな国際情勢全般に関する私たちの見方を述べておきたい。それは、現在は20世紀の世界恐慌(1929年)から世界大戦に至った1930年代に匹敵する、時代の転換期に立っているという認識である。30年代は、恐慌への対応として各国が自国本位の政策を展開し、ナショナリズムの高揚と社会不安の増大の中でファシズム・軍国主義などの権威主義体制が成立して戦争へと突き進んだ。現在は、冷戦終了後、グローバリゼーションが進展する中で各国間および各国内での格差が拡大し、それに宗教対立・民族対立などが複雑に関係して国際的な不安定性が高まっている状況下にあり、そこに新型コロナウイルスのパンデミックを迎えている。コロナ禍への対応による経済的ダメージは甚大であり、ワクチンの開発・接種によって新型コロナウイルス自体の脅威は解消されていったとしても、各国経済が本格的に回復・成長していくには時間がかかるといわれている。こうした中で、巨大な経済力・軍事力を背景として既成の国際秩序を自らに都合がよいように変更しようとしている中華人民共和国(以下、「中国」)の存在感は増大する一方であり、世界は権威主義体制と自由・民主主義体制の二つに分裂していくおそれもある。さらには、自由主義、民主主義を普遍的価値として重視してきたアメリカ合衆国(以下、「アメリカ」あるいは「米国」)やヨーロッパ諸国においても、これまでの政治体制に強い不満を持つ人々が増え、自由主義や民主主義が危機に瀕しているといわれる。
こうした状況を考えた場合、日本という国が進むべき道は、自由主義や民主主義を維持し、発展させていくための国際社会の原動力の一つとなることであろう。第二次世界大戦以前の日本は、軍事に偏った権威主義体制の下で戦争に突き進み、他の国々に災禍を広げ、敗戦に至った。戦後の日本はその反省に立ち、また30年代からの教訓で第二次世界大戦後につくられた国際的な協調体制・自由主義体制を享受することで成長・発展した。自由で民主主義的な体制の維持・発展こそ日本の進むべき道であることに、多くの日本国民は異議を唱えないであろう。時代の変革期にあたって、日本が進むべき方向性を見据え、そのための政策を考えていくこと、それこそが、今、求められる安全保障戦略の議論である。
安倍・菅政権が壊したもの
われわれは、どこにいるか
1. 安倍政権下、日米の軍事的一体化が進んだ
安保法制による集団的自衛権の容認と平時からの自衛隊による米艦防護など、米軍を守るための一体化から、さらに進んで敵基地攻撃能力の保有が展望され、長射程ミサイルの取得・開発が進み、また計画されている。
戦後日本は、軍事面での安全保障をアメリカに依存しつつ、自らの国力に応じて自国の防衛力を整備してきた。そこでは、米国に基地を提供する一方で、戦争に巻き込まれないよう、専守防衛に徹し、自衛隊の役割を防御に限定し、「米軍の戦闘行為とは一体化しない」という制約を課してきた。いま、その制約を越え、米国とともに対象国に向けて攻勢をとることが可能になっている。
仮に米中が戦えば、地理的に最前線に位置することになる日本への影響は計り知れない。米中が互いに対立姿勢を先鋭化するなか、「米中戦争に巻き込まれる」という同盟のジレンマが現実化する危険が増大している。
この現実を踏まえ、いかに日本の安全を確保するかが問われている。
2.安倍・菅政権の「説明しない政治」によって国民の政治への信頼が低下している
政治の基本は、国民の信頼である。安倍政権による「説明しない政治」が国民の政治への信頼を失わせたことは、新型コロナパンデミックとの闘いにおいても明らかになった。説明責任や情報公開は民主主義の基盤であるにもかかわらず、日本において、その基盤が揺らいでいる。
現代は、気候変動による大規模災害の多発や未知の感染症の蔓延、あるいは大国間の偶発的な衝突というリスクに満ちた不安定な時代である。必要なのは科学的知見に基づく論理的考察であり、それによって国民がリスクを認識し、政府が対応策を打ち出し、これを実感することによって初めて国民は不安から解放される。「説明しない政治」は、全国民的な危機対応を困難にする。続く菅義偉政権も、科学的リスクを国民と共有する努力を怠ってGoTo政策に固執した結果、感染拡大を招き、国民の政治不信を高めた。
私たちは、パンデミックの対応においても強権的に国民を隔離・統制することで危機を克服する全体主義を決して望まない。リスクと不安の時代にあって、民主主義の活力を回復させるための「政治のあり方」が問われている。これは、外交・安全保障政策についても変わらない。日本が直面するリスクを正しく認識し、不安の裏返しとしての軍事力に過度に依存した願望に走ることなく、穏当で説明可能な、わが国に相応しい目標設定が求められている。
日本のおかれた安全保障環境
われわれを取り巻く世界はどうなっているか
1. 米中対立と安全保障ジレンマの時代
トランプ政権の後半、米中の対立関係はいっそう先鋭化した。米国は、台湾海峡や南シナ海に軍艦や爆撃機を派遣し、空母機動部隊を集結させた訓練を行うなど、中国に対する軍事的プレゼンスを強化した。中国も、台湾周辺での海・空軍の活動を活発化するとともに、米海軍艦艇や基地への攻撃を想定したミサイル演習を行うなど、軍事的緊張が激化した。
米国は、伝統的な対中関与の政策を否定し、中国封じ込めのための同盟国・友好国による新たな連携を模索した。また、台湾の国連加盟を主張するとともに、高度な武器の売却や閣僚級の高官派遣など、米中台三者によって共有されていた「一つの中国」という、台湾海峡両岸関係の基本的認識を否定する動きが見られた。
さらに米国は、貿易の不均衡是正のための追加関税のみならず、国家安全保障を理由とした鉄・アルミニウム等の関税引き上げを行うとともに、ハイテク分野での中国企業の締め出しや、中国経済との相互依存関係を分断するデカップリングまでも追求を始めている。中国も、中国を批判する貿易相手国への制裁や、戦略物資の輸出規制などを可能とする国内法を制定して対抗した。
こうして、米中両大国は、軍事のみならず、政治・経済面をも含めた全面的な競争・対立関係に至った。その背景には、米中の相互不信の顕在化という構造的要因がある。すなわち、米国には、「米国を中心に築かれてきた国際秩序を中国が変えようとしている」との懸念があり、他方、中国には、かつて西側列強によって形成された秩序そのものへの不信と自らの力への過信、さらには、米国による干渉が国内の安定を脅かすことへの恐怖がある。
米国は、バイデン政権に替わり、「米国ファースト」という言葉に象徴される一国主義と比べれば、協調的な外交政策へ変化すると言われるが、対中国政策については強硬的な政策に変化はなく、人権面でより厳しい対応を求めることも予想される。こうした構造的要因が存在する限り、競争・対立の米中関係に大きな変化はないと見られる。かかる対立と相互不信のもとでは、いずれの側の行動も相手の対抗行動を誘発する力学が作用する。経済的には制裁の応酬、政治的には非難の応酬があり、軍事的には一方の防御的行動が一方を挑発して対抗的な行動を生み、緊張を高める「安全保障のジレンマ」の顕在化が懸念される。大国間の競争・対立の構図は、周辺国のみならず、世界を不安定化させる重要な要因である。
バイデン政権下の米国の政策は、トランプ時代とは異なり、対立の中にも国際ルールを形成していく方向に向かっていくと考えられる。ただし、コロナ禍への対応を最優先とし、巨額の財政支出を行う米国に、中国に対抗するための巨額の軍事支出を追加する余裕はなく、そのため、トランプ政権時代に傷ついた同盟関係の修復を急いでいる。並行して行われるのは、米ソ冷戦時代の経験を生かした危機を管理するための体制の構築であろう。そもそも相互に大量の核兵器を有している両国にとって、最終的に核を使用する段階まで軍事対立をエスカレートさせることは非現実的な究極の選択であり、双方とも求めていない。また同盟国は、米国の戦争に「巻き込まれる」ことを恐れているが、米国も同盟国が中国との対立をエスカレートさせ、同盟国の軍事的対立に「巻き込まれる」ことを望んでいない。米ソ冷戦時代の戦略は、相手に勝つための戦略ではなく、ブレジンスキーの言葉を借りれば「負けないための戦略」であった。
バイデン政権の高官には、かつての政権で外交や安全保障を担当していた経験をもつ実務者が数多く登用されている。トランプ時代のように危機をあおるのではなく、中国の影響力拡大の阻止という目標を掲げつつ、同盟国とともに危機管理のルール化とルールの下でのゲーム化が進められていくと考えられる。
米国の政策は高度な戦略的思惑の中で進められることになる。一方の中国も長期的視点からの戦略に基づいて拡大積極政策を採っている。
米中が牽制を強める中において、日本が軍事的な技術論に傾斜していてよいはずはなく、国益のための長期的視点に立った議論が十分に行われねばならないし、その上で、米中の軍事衝突を避けるために日本にどのような貢献ができるか冷静に検討し、米中の理解を得て、両国の「架け橋」とならなければならない。
2.米中軍事バランスと前線化する日本列島
中国は、台湾や南シナ海をめぐる武力紛争に備えて、米国の介入を阻止するための接近阻止・領域拒否(A2/AD)の能力を向上させるべく、中距離・短距離ミサイルや潜水艦の能力強化に重点を置いた軍拡を進めるとともに、米軍の指揮・通信・情報システムの基盤となっている宇宙・サイバー領域における妨害能力を高めてきた。今日、米軍にとって、西太平洋・東アジアで中国のミサイルから安全な地域は減り、行動の自由が失われている。
米国は、当該地域における軍事的優位性を回復させるべく、インド太平洋軍の態勢を変換しつつある。すなわち、大規模な地上基地や空母などの大型艦艇が中国のミサイル攻撃に対して脆弱であることから、兵力を小型化・分散化して、精密打撃ミサイルのプラット・ホームを増やし、相手の攻撃目標を分散しつつ、海洋におけるミサイルの打ち合いに勝利する態勢を構築することで、失われつつある優位性を回復しようとするものである。同時に、西太平洋における米軍のハブであるグアム島の防衛のための地域統合ミサイル防衛網を、同盟国と共同して構築しようとしている。
そこでは、南西諸島を含む日本列島が前線拠点として重視される。同時に、自衛隊のミサイル防衛や長射程化したミサイルの能力が米軍の統合作戦の一部に組み込まれ、ひいては、米中の戦争となった場合には、沖縄や日本本土の基地が攻撃されるリスクが高まることに留意しなければならない。
米軍において、抑止力とは、戦争に勝つことができる能力を意味している。一方、日本国内では、「抑止力があれば戦争にならない」との認識がある。米国の新たな軍事戦略の意図が「抑止力強化」であっても、前線に位置する日本としては、「抑止が破たんした場合に戦場になる」という覚悟を国民に求めなければ、リアリティのある政策とは言えない。
3.沖縄米軍基地をめぐる状況変化
米中対立の激化と米国の新たな対中軍事戦略は、前線拠点となる沖縄の基地のあり方に大きな変化をもたらす可能性がある。
第一に、米海兵隊の主要な役割は、離島に分散して、一時的なミサイル発射施設や航空基地を構築することに変化する。この構想の下で、新たな部隊がどこに配置され、いかなる装備を持ち、いかなる運用をするか、また、米軍再編に関する2012年の日米合意の見直しにある「実戦部隊9000人の沖縄から日本国外への移転」が計画通り進むのかも明らかではない。
第二に、新対中戦略のなかで、普天間基地に所在する第31海兵遠征部隊(31MEU)について、その役割や、引き続き沖縄に駐留しなければならないことについての理由の説明がなされていないという問題がある。
辺野古の新基地は、この31MEUのオスプレイなどのヘリ部隊を収容する施設として計画されている。その運用によっては、辺野古新基地の必要性はもとより、同部隊が沖縄に常駐する必要性すらなくなる可能性もある。
第三に、近年、辺野古新基地予定地に軟弱地盤が存在することが明らかとなり、防衛省は、工期を当初の8年から12年に延長し、費用も当初予定の2.7倍にあたる9300億円に増えると、大幅に上方修正した。それでも、この範囲で建設が可能かどうかについては、専門家から疑問の声があがっている。そこに、ユーザーである海兵隊の態勢変換という事情が加わった。つまり、1兆円前後の莫大な費用をかけるにもかかわらず、完成時には海兵隊のニーズに合わない壮大な無駄に終わるおそれが出てきたことは否定できない。
言い換えれば、「普天間の危険性除去と抑止力の両立」のために「辺野古が唯一の選択肢」としてきた政府の論理は破たんしている。2022年には本土復帰50周年を迎える沖縄で、こうした「説明しない政治」が続いていることは、日本の民主主義の観点から見て、深刻な問題であると言わざるを得ない。政府と国会は、具体的な議論を通じて、最低限、沖縄県民が納得するに足りる説明をしなければならない。
沖縄の米軍基地問題は、日米安保体制の負担をどう分散するかという政治問題である。軍事態勢とは切り離して考えるべき問題であり、辺野古新基地建設に反対の声を上げ続ける沖縄の民意に向き合うのか、目を背けるのかという問題である。なお在沖海兵隊基地がすべて返還されたとしても、米空軍嘉手納飛行場と嘉手納弾薬庫を合せた面積は本土にある在日米軍の主要な6基地である三沢、横田、厚木、横須賀、岩国、佐世保を合わせた総面積より広く、沖縄の負担はなお大きいことに留意すべきである。
日本社会には米軍受け入れ自体についての支持は相当程度存在するものの、米軍も日本社会のルールに従うべきであるという意識は強い。2020年の普天間基地における消火剤流出事案では、日本側の基地立ち入りが認められたものの、土壌サンプルの提出は拒否された。また、新型コロナウイルスに感染した米軍人らが入国し、米軍人のクラスター(集団感染)の発生が複数確認されている。このように、現在の日米地位協定の運用では、様々に起きる事態に対応できていない現実がある。安全保障環境が厳しさを増し、本土を含めて米軍の訓練やローテーション配備の頻度が高まることが予想される状況でもある。
日米地位協定の改定と抜本的改善は避けて通れない課題である。
4. 南シナ海・尖閣における中国の現状変更の試み
中国は、力による現状変更の試みを続けている。南シナ海に構築した人工島の軍事施設化を進めるとともに、フィリピンやベトナムの排他的経済水域(EEZ)のなかで、当該国の公船を排除しつつ、石油探査や漁業を行うなどの行動をとっている。わが国固有の領土である尖閣についても、多数の公船を接続水域に配備するとともに、長時間にわたって領海に侵入する事案も多発し、日本の安全保障上の大きな不安要素となっている。
中国は、海軍ではなく日本の海上保安庁に当たる海警局や漁船団を使用し、「サラミ・スライス」といわれる漸進的な方法で既成事実を作ってきた。これは、武力行使に至らない「グレーゾーン」といわれる事態であり、米国は、軍事的に優位であった時期でも、有効な阻止行動をとれてこなかった。米海軍による南シナ海における「航行の自由作戦」が常態化しているが、中国による南シナ海支配の動きは止まっていない。
2020年末、米大統領選挙後の菅首相との電話会談で、バイデン氏は、尖閣諸島に日米安保条約第5条が適用されることを明言したが、こうした政治的宣言が尖閣周辺における中国海警の動きに影響を与えることはなかった。
中国は、米国との戦争を望んでいないが、一方の米国も、どこまでが許容限度かという「レッドライン」を示せていない。中国による現状変更に対する米国の軍事的介入の意志は、曖昧である。その曖昧さが抑止に寄与するという見方もあるが、中国はグレーゾーンの範囲で目的を達成しているのであって、抑止されていないのが現実である。
中国海警の強化と船舶の大型化が進み、東シナ海・南シナ海のいずれにおいても、実効支配を主張する他国の法執行機関や軍隊の艦船を量的質的に凌駕している。もっとも、尖閣諸島についての中国公船による領海侵入は近年大幅に増加したが、南シナ海での他国との領土紛争とは異なり、中国は、日本の海上保安庁の巡視船を排除・攻撃するような行動には至っていない。これは、日本に対する実力行使には海保や自衛隊からの反撃があり、本格的な日中間の紛争に発展すると認識している結果であると思われる。
他方、海保の対応能力は、ほぼ限界に達していると言われている。だからといって、自衛隊が海上警備行動で出動したとしても、外国公船に対する強制措置をとることはできないだけでなく、相手もこれに対抗して軍隊を出すことが予想され、かえって事態を拡大するおそれがある。また、仮に島を占拠された場合に自衛隊が奪回したとしても、第2波・第3波の占拠にどこまで対応できるのかという問題もある。大国に対して、力で対抗するのは限界があると言わざるを得ない。だからといって、米軍の参戦を求めれば、戦域は尖閣に止まらず、沖縄や九州を巻き込んだ本格的な戦争に発展する可能性も否定できない。
中国は、その能力に任せて、今後も尖閣周辺での行動を継続・拡大することが予想される。日本は、その圧力に耐え、抵抗の姿勢を維持しつつ、政治的解決の道筋を息長く模索する以外にない。そのためには、海上保安庁の能力の拡充が急務である。警察力である海保が前面に出ている間は、軍事衝突は避けられる。しかし、中国が「海警法」の改正によって実力行使へのハードルを下げ、また中国海警の能力自体も増強されている現状からは、海保の対応能力がいつ限界に達するか、予断ができない状況である。海保の能力拡充は、安全保障環境の維持のためにも極めて重要である。
5.北朝鮮の動向と拉致問題
朝鮮民主主義人民共和国(以下、「北朝鮮」)は、核・ミサイル開発に伴う経済制裁、新型コロナウイルスの影響による中国との貿易の激減、台風による被害、といった経済的な三重苦の状況にある。トランプ氏と金正恩氏のトップ会談による制裁解除のシナリオも実現しなかった。経済的苦境のなかで、従来の軍事優先から国内経済の立て直しに目標を転換させている。
北朝鮮は、各種ミサイルの実験をくりかえし、「核戦力の完成」を宣言した。その能力は軽視できないものの、十分に実証されたとは言えない。また、国内の態勢を見ても、対米戦争に向けた準備もなく、戦争に耐える国力があるとは考えられないことから、「北朝鮮の脅威」が差し迫ったものととらえることはできない。対米抑止の強調は、経済優先に転換するための国内向けのメッセージであり、米国に対する外交カードとして活用されている。実際の能力以上に虚勢を張っていると見るべきであろう。米国の戦略見直しのなかでも、北朝鮮についての言及はほとんどない。
一方、米中対立が台湾や香港の人権問題をめぐって激化するなかで北朝鮮の一連の問題に関心が払われなくなることは、北朝鮮にとって深刻な事態といえる。そうした状況の打開を狙って挑発的行動に出る可能性はあるが、体制維持を最大の目標とする金正恩氏の北朝鮮にとって、勝算のない戦争によって得られる利益は何一つない。
安倍政権が最優先の外交課題としてきた拉致問題は、全く進展を見ていない。北朝鮮は、菅義偉政権となった後も、「拉致問題は完全に解決済み」との声明を出した。他方、日本にとって北朝鮮との対話の窓口は皆無に等しい。事実上唯一の交渉窓口であった米国政府も、新政権がいかなる対北朝鮮政策をとるか不明である。米国や中国や大韓民国(以下、「韓国」)に支援を依頼するだけでは、拉致問題解決の展望がないことは明白である。
また、北朝鮮にとって、「核」は体制維持の最後の拠り所である。これを放棄させるためには、長期にわたる体制保証という代償が必要となろう。一方、拉致被害者家族の高齢化を考慮すれば、残された時間は多くない。その認識を踏まえ、「核放棄なくして交渉なし」といった硬直した発想を捨て、拉致問題解決を含む国交正常化プロセスのなかで核放棄の動機を強めるなど新たなアプローチが求められる。
6.最悪の日韓関係
戦時の日本による韓国人徴用工や従軍慰安婦への個人賠償問題をめぐって、日韓の対立が続いている。2019年、日本は、対抗措置として、韓国への半導体材料の輸出審査を強化し、輸出管理の手続き簡素化の対象国である「ホワイト国」から韓国を外す処置をとったが、これは、国連としての制裁ではなく、二国間の対立に日本が経済制裁的手段を用いたケースである。韓国は、日韓の防衛情報共有の枠組みである日韓秘密軍事情報保護協定(GSOMIA)の延長拒否でこたえようとし、また、半導体材料などの自主技術開発を進めて対抗した。政治対立が経済、安全保障にまで影響を及ぼす事態になっているが、それでもなお、政治対立の解消に向けた道筋は一向に見えない。
両国間の妥協点が見いだせないまま、日本では安倍政権が交代し、韓国の文在寅政権も国内の基盤が揺らいでいる。弱体化する政権にとって、政治的妥協はますます困難となるなかで、在韓日本企業への強制執行の法的手続きは進み、残された時間はなくなりつつあり、早急な決着が望まれる。
日韓対立の基礎にあるといわれている双方の歴史認識問題は複雑で、現状では容易に解決の糸口が見えない。もっとも、日韓関係は、相互にとって極めて重要な二国間関係であるという事実は、中国が対外積極政策をさらに拡大する中において、一層増すばかりである。両国は、対馬海峡を挟んで接する隣国であり、歴史的に長い関係があるだけでなく、安全保障面でも共通の課題に直面している。
従来、両国の安全保障は、北朝鮮の脅威を中心に論じられ、米国をハブとする事実上の準同盟関係にあると認識されてきた。今日、米中対立激化のなかで、日韓は、黄海・東シナ海を挟んでともに中国と対峙し、中国の海洋権益をめぐる言動が両国にとって共通の挑戦となる局面を迎えている。中露両国の軍用機が日韓の防空識別圏(ADIZ)を飛行する事案も発生し、米国による韓国への高高度防衛ミサイル(THAAD)の配備が中国の激しい反発を生んだことも記憶に新しい。
同時に日韓と中国は、FTA交渉に関する三か国の対話枠組みを持っている。後に述べる東南アジア諸国連合(以下、「ASEAN」)を中心とした東アジア全体の枠組みと並行して、この枠組みを北東アジアの秩序形成に向けた対話の場として発展させることも可能だろう。
日韓が「個別に対応し個別に困難を強いられる」のではなく、同じ方向性をもって連携して中国に向き合うことが重要であるとの認識が広く共有されねばならない。
7.日露関係と北方領土
北方領土問題を解決して平和条約を締結する課題が停滞している。ロシアは、領土の割譲を禁ずる憲法改正を行うとともに、菅義偉政権に対して、平和条約締結後に二島を引き渡すという1956年の日ソ共同宣言を基礎とした交渉を行うことを確認している。これは、二島に関する国境確定に交渉の目的を限定することを意味する。日本は、四島返還の主張を事実上断念するか、交渉の機会を閉ざすかの選択が問われている。
相対的に力を落としてきた大国ロシアは、自国の利益を優先し、米国との対立のなかでそれを安全保障上の利益と関連付けて正当化する傾向がある。公正な戦後秩序回復の問題としての北方領土問題も、米ロという大国間関係の文脈を離れて解決することはできない。
ロシアは、ミサイル攻撃に対して核による反撃を辞さない新たな方針を公言し、迎撃が困難な極超音速滑空型の中距離ミサイルを開発している。ロシアは、これを欧州に配備しない方針を表明した(それは、このミサイルの開発が中距離核戦力全廃条約(INF)に違反していたことの証左でもあるが)。一方、新型ミサイルが極東に配備され、米国が第一列島線に中距離ミサイル配備を進めるならば、日本は、新たな中距離核ミサイル軍拡競争の舞台となる。
1956年以来半世紀以上にわたって停滞していた領土交渉を、中距離ミサイル配備競争という新たな冷戦的対立のなかで進展させようとすること自体に無理がある。
米国の中距離ミサイル配備を積極的に進めることによって新たな米ロの中距離核全廃につなげるといったことは、中国という強大なアクターが存在する今日の極東では不可能である。日本を新たなミサイル軍拡の舞台にしないための核・ミサイル軍備管理が早急に求められている。そうした米ロ大国間関係の安定の上に、新たな領土問題解決の展望を作り出さなければならない。
8.「インド太平洋」の現状と協調的安保への道
安倍首相が提唱した「自由で開かれたインド太平洋(以下、「FOIP」)」 をめぐり、各国の思惑は交錯している。日本では、FOIPは中国の「一帯一路」に対抗するものとして捉えられ、2017年に初めて開催された日米印3カ国による共同演習「マラバール2017」のころから強調されるようになった。 なお、日米間ではFOIPの実現に向けて協力強化が確認されてきているが、米国のFOIPでは対中強硬姿勢が色濃い。
2018年にはフランスが「インド太平洋(Indo-Pacific)」についての新たな外交戦略を策定し、19年にASEANが、そして、20年にはドイツ、オランダも「インド太平洋」についての外交戦略を策定した。もっとも、中でもASEAN諸国においては、中国への刺激を避け中国を囲い込むような政策への参加には後ろ向きである。
「インド太平洋」という概念が、中国と敵対することも、中国を排除することもできず、米中の二者択一はできないと考える諸国によって広く共有されることは、それだけ中国の存在が無視できず、各国が米中いずれか一択ではない選択肢を求めていることの証左でもある。日本も、その後の日中関係の改善もあり、FOIPを「戦略」から「構想」と言い換え、中国の一帯一路に対峙する概念ではないと意思表明し、中国参加の可能性すら示唆している。
この変化の中で、FOIPは「敵」を前提とした集団的安全保障のみならず、協力を前提とした協調的安全保障の側面をも垣間見せるようになり、内容についても、法の支配・海洋秩序に止まらず、自由貿易や環境破壊、人権など、国際協調を必要とする幅広いテーマを包摂する傾向をもちはじめている。
このFOIPは、中国に対抗する概念から、中国を排除せず、共通の利益に基づく合意を目指すための思考枠組みとして、米中対立を基調とする国際環境のなかで新たな協調をもたらすものとなる可能性もある。
他方、近年、日米およびオーストラリア、インドの四か国の連携を目指すQUAD(4ヶ国安保対話)は、軍事協力の側面が際立つようになった。インドは2020年、中国との国境紛争を境にマラバール演習へのオーストラリアの参加を受け入れた。米国は、インドとの軍事情報の共有や武器の輸出を促進し、日本も、インドとの物品又は役務の相互の提供に関する協定(ACSA)や、オーストラリア軍の受け入れに備えた地位協定の締結を急いでいる。他国との連携の重要性を認識しつつも、QUADが中国に対する軍事偏重の運用とならないよう注意を払っていく必要がある。
中国は、現在のこうした動きを冷戦的軍事同盟の復活と非難し反発を強め、例えば、オーストラリアに対する経済的制裁を発動するなどしている。他方で、その強圧的な姿勢が、さらに欧州やASEANのなかに対中警戒感を高め、結束を促すという反作用ももたらしている。
包括的なFOIPが協調的安保のきっかけとなることで、幅広い連携の可能性が開かれ、国際協調の観点から中国の強圧的な行動を制約する有力な手段となることが期待される。
9. 混迷する中東
トランプ政権のもとで、中東安定のための枠組みが揺らぎ続けてきた。シリア内戦が人道上の危機を生み、イラン核合意からの離脱や2020年初頭の革命防衛隊司令官殺害がイランの反米姿勢を強め、地域の緊張を高めるとともに、イエメンにおけるイランとサウジアラビアの「代理戦争」が極めて深刻な人道危機を招いている。ヨルダン川西岸へのイスラエルの入植を容認するトランプ政権の「パレスチナ和平案」は、中東問題の核心であるパレスチナ問題を妥協不能の状況に追い込んだ。
ここまで混迷するに至った状況について、だれも有効な手立てを講じる意志も能力も持たない現実がある。だが、中東が日本のエネルギーの主要な供給源であるとともに、国際社会全体に影響を与える戦争の発火点となりうる現実に変化はない。
その中東に日本はいま、自衛隊を派遣している。アフリカのジブチを拠点とするアデン湾におけるソマリア海賊対処とアラビア海における「調査・研究」と称する情報収集活動である。海賊の被害は激減する中で、初の海外拠点をジブチにおいた中国を牽制する役割が濃くなり、一方の情報収集活動はイランに対抗する米国の補完的役割を担う。看板と中身にズレが生じてきた自衛隊に、いかなる役割を与え、いかに危険を回避するかは、引き続き政治がたえず注意を払うべき課題である。同時に、日本が中東に対して何ができるか、との観点から、日本は中東の安定に向けた貢献を十分にしているか、自衛隊派遣が必要不可欠であるのか、が問われ続けなければならない。
抑止政策の限界と安全保障の新たなマインドセット
われわれは何を考え、何をなすべきか
これまで、日本と世界の現状を俯瞰してきた。対米、対中関係に絞った項目を設けなかったのは、それぞれの大国との関係が多岐にわたっており、特定の視点では括り切れないためである。ただ、これまで述べてきた認識のなかに、基本的な視点は含まれていると考える。
米中関係という巨大なジグソーパズルでは、一つのピースが全体の絵柄に影響する。一つの切り口で見る場合には、反(親)米・反(親)中といったバイアスに陥ることを避けがたい。
ここでは、日本の政策論議に対する問題提起を行う。まず、今日の大きな時代の変化のなかで、従来、議論の対象とされず、いわば思考停止状態にあった抑止力を中心とする政策のマインドセットについて、さらに、その具体的な適用としての防衛政策論議の課題について述べる。
抑止とは、攻撃に対して反撃する意志と能力を示すことによって、相手に攻撃を思いとどまらせる作用である。それは、反撃する(言い換えれば「こちらも戦争を厭わない」という)意志と能力を相手が正しく認識し、その結果、こちらが期待する通りに攻撃を思いとどまる(我慢する)という、論理である。
また、抑止とは、相手に一定の行動を我慢させることであるから、「相手が何をすれば許せないのか」の共通認識があり、かつそれが、相手の我慢可能な範囲であることが、安定した抑止関係を構成するために必要な条件となる。裏を返せば、「何をしなければ戦争にならないのか、その範囲であれば、戦争に訴えずに我慢できる。したがって、戦争しない方が自分の利益になる」という認識を相手に与えること(安心供与)が、安定した抑止関係の前提である。現在の米中関係をみる限り、その抑止への理解が欠落しているといわざるを得ない。
そのため、米中間で「安全保障のジレンマ」が生まれ、日米同盟に依存して防衛力強化を図る日本に「同盟のジレンマ」を突き付けている。いま必要なことは、この二重のジレンマの中でいかにリスクを低減しつつ、自ら可能な目標を立てるかということだ。
抑止の論理に従えば、米中関係が安定するためには、相互に我慢可能な限度を共有することであり、それによって共通のルールを持つことが必要だが、それには、10年単位の時間を要すると思われる。
その間、日本にとって最大のリスクは、米中の対立が管理不能な状態となって戦争に至ることである。米中戦争の回避をわが国の安全保障の最大の目標と位置づけるべきである。そのための手立てとして、現在、日米同盟の抑止力強化が図られているが、安全保障ジレンマの時代にあって、そのことがかえって戦争の誘因となりかねない危険を認識しなければならない。
抑止は、相手への安心供与なしには安定したものにはならないので、抑止力だけを論じても、それだけで安全保障政策として完結しない。抑止を補完し、機能させ、破たんさせないための対話の努力を安全保障政策の「車の両輪」と位置づけることが不可欠である。
米中という超大国相手に、日本にできることは限られるかもしれない。しかし、米中戦争の戦場となる国として、米中戦争に影響される他の東アジア諸国と共同して、対話を求める努力を始めなければならない。
これは、米国の抑止力を否定するものではなく、それが、地域の安定化要因として正しく機能することを求め、また、中国への過度な強制・挑発となってかえって戦争の危機を高めることがないようにするものである。そのためには、現実に進行する抑止強化の政策を一律に否定するのでもなく、むろん、一律に肯定するのでもなく、具体的な自衛隊の運用の限度、米軍の配置やわが国を拠点とする作戦行動のあり方を議論しなければならない。
特に日本は、米中対立の影響をもっとも強く受ける国のひとつであることから、そのミドルパワーとしての力を生かし、他の東アジア諸国と連携しながら地域の平和構築の水先案内人として地域の安全保障に貢献するべきである。
また、近時、イギリス、フランス、ドイツなど欧州諸国がインド太平洋の安全保障問題に関心をもち、軍事力の派遣などを行うようになっているが、インド太平洋地域が国際経済発展の中心になってきていることが、その背景にある。この欧州諸国の動きが、中国との対立に拍車をかけ、国際社会を米中のブロックに分裂させる流れを加速する結果に陥らないように最大限の注意が必要である。むしろ、今こそ日本は、アメリカはもとより、ヨーロッパ世界とアジア地域の間の「架け橋」となり、協調的な安全保障システムを構築していくためのリーダーになるべきである。
唯一の戦争被爆国であるという事実は、世界政治のなかで、日本に特殊な立場を与えてきた。また、憲法第9条を持つ国、沖縄戦という民間人を巻き込む悲惨な戦争を経験した国、東アジアとの連携のなかで経済発展を遂げた国として発信するメッセージも、今なお世界にとって意味あるものとなるだろう。「法の支配・自由・人権・民主主義」という価値観に止まらず、「非戦・非核」という価値観を発信する国であり続けることが日本の国際貢献となろう。
提 言
■世界は、構造変化の時代にあり、相互不信が「安全保障のジレンマ」を顕在化するリスクを高めている。民族・人種・宗教・社会的階層の分断が進み、国内的・国際的不安定化と対立を助長する一方、自然災害・感染症の蔓延のなかで、人々の不安が拡大している。
■変化と不安の時代にあって、国民が安心して生活できる国と社会のあり方を守ることが本来の安全保障である。それは、軍事のみで成り立つものではなく、また、科学に基づく国民への説明が強く求められている。安全保障に必要なものは、広角的視野と説明責任である。
■戦後日本は、「東西冷戦下における安定的抑止」と「多国間協力による連携」という国家像のもとで発展した。
いま再び日本が、世界の架け橋として、対立から協調に導く役割を果たす必要がある。
■軍事面では、米中対立が戦争に至らないようにすることが喫緊の課題である。抑止力を高める一方で、抑止を安定化させるための「安心供与」と、信頼醸成・多国間協力を通じた対立の管理を「車の両輪」として機能させなければならない。
■これらの観点から私たちは、政治における議論が、戦術的抑止のレベルにとどまっている現状を危惧する。
直面する課題について
■ 米中対立における前線国としての課題
米中対立のなかで、防衛努力は重要であるが、戦争となった場合の日本の被害が甚大となることへの思慮も不可欠である。米国の戦略に協力する場合には、「戦争に巻き込まれない」心構えが必要である。米中の架け橋として、また、地域の架け橋としての役割を追求すべきである。
この観点から、
●米軍の中距離ミサイルの配備など、日本をミサイル軍拡の場とする政策に反対すべきである。
●自衛隊ミサイルの長射程化や艦艇のプレゼンスなどがかえって地域の緊張を招くことがないように配慮すべきであり、「敵基地攻撃の禁止」など自衛隊の運用に関する新たな「歯止め」を設けるべきである。
●沖縄への過重な基地負担は、日米同盟の最大の不安要素である。膨大な経費を必要とする辺野古新基地の建設は、取りやめるべきである。また、米軍基地の県外への分散を進めるとともに、日米地位協定の改定を目指すべきである。
●日中の紛争要因である尖閣については、力だけで守り切ることが困難なことを踏まえ、海上保安庁の態勢を強化し、加えて、日中間の政治的危機管理体制を構築すべきである。
●在日米軍駐留経費負担については、コロナ禍で財政がひっ迫するなか、合理的根拠に基づかない安易な増額をすべきではない。
●「インド太平洋」諸国との連携を進めるべきである。その際、対中封じ込めと軍事協力一辺倒ではなく、地域の協調関係を推進するためのアジェンダの包括性と当事者の多様性を追求すべきである。
■ その他の外交課題
●拉致問題については、核放棄の先行性にこだわらず、核放棄のプロセスとの並行のなかで優先的解決を図るべきである。
●北方領土問題については、事実上の2島返還すら困難な現状に鑑み、米ロの戦略的安定を目指すなかで、新たな交渉枠組みを追求すべきである。
●日韓関係については、歴史認識の隔たりをなくすことの困難さを踏まえると同時に、自由と民主主義という価値観の共有をベースとして、対中政策の面で新たな方向性の一致を目指すべきである。
●トランプ政権によって混迷を増した中東については、パレスチナを含む当事者関係の安定と内戦による人道危機に対し、自衛隊ができることには限界があることを踏まえ、日本の役割についての新たな政策パッケージを策定すべきである。
●日本の発信力の源泉としての「唯一の戦争被爆国」であること、憲法第9条を持つ「非戦の国」であることを活かし、多国間枠組みの創設とその活性化を目指すべきである。また、核兵器禁止条約締約国会議に積極的に参加し、地域の信頼関係を醸成すべく核廃絶に向けた主導的役割を担うべきである。