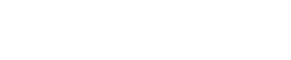新外交イニシアティブ代表 猿田佐世
15日で沖縄「本土復帰」50年を迎える。「復帰50年」には多くの含意があり、その一つ一つが今の沖縄がおかれている状況について私たちに問いを投げかける。
なぜ「復帰」か。先の大戦中、本土決戦までの時間稼ぎとも言われた4人に1人が命を失う激烈な地上戦を経ての、27年の米国による占領統治があったからである。なぜ「日本」に復帰したのか。450年続いた琉球王国が「琉球処分」により日本に併合された歴史があるからだ。
「50年」経つが、基地撤去と平和を求める「反戦復帰」運動の成果であったにもかかわらず、復帰後も基地がなくなることはなく、現在も名護市辺野古で新基地建設が進んでいる。「平和憲法の下への復帰」が希求されたが、今なお、米軍による犯罪や爆音などで基本的人権が侵害される状況が続き、「沖縄は憲法番外地」とさえいわれる。
復帰に先立つ1971年11月17日、米軍統治下の琉球政府行政主席であった屋良朝苗氏は、沖縄の総意をまとめた「復帰措置に関する建議書」を手に首相らに直訴すべく東京に飛んだ。「建議書」は、米国が自由諸国防衛の美名の下、膨大な基地を建設し、基地の中に沖縄がある状況にあること、軍事優先政策の下で基本的人権すら侵害されてきたこと、沖縄が国家権力や基地権力の犠牲となりすぎてきたこと等を訴えていた。
しかし、氏が羽田空港に降り立つ数分前、基地の固定化を認めた沖縄返還協定案が衆議院特別委員会で強行採決されていたのである。氏の日記には、「県民の気持ちはへいり(破れた草履)のように踏みにじられるものだ」と記されている。
今月7日、玉城デニー知事は、復帰50年を機に、あるべき沖縄の将来像を描いた「新たな建議書」を発表した。これは本土に届くのか。
歴代首相をはじめ、辺野古基地建設を推進する側は「沖縄に寄り添う」という言葉をよく口にする。
私は、この10年、米首都ワシントンに辺野古基地建設反対の沖縄の声を届けてきた。当初、米専門家等から「米軍の展開を軍事的に細かく分析すれば、新基地建設の必要性が理解できるだろう」と言われ続けた。そこで、安保専門家とともに3年間研究をし、米海兵隊の運用などを軍事の視点から分析し、それでも辺野古新基地は不要であるという提言を作成して、ワシントンに持参した。すると「細かい軍事的な分析ではなく、政治状況も含めた大きな視点で見なければ」と、米軍の運用実態についての議論すら遮られた。痛感した。辺野古基地建設についてさまざまな必要性が語られるが、結局は沖縄の人々の意見に耳を貸す気があるかどうか、その姿勢の違いのみなのだ。
首相らの「沖縄に寄り添う」との発言は、その多くが「沖縄が拒否する辺野古の新基地建設は行うが、経済的支援などで悪くはしないから、こちらも一生懸命なのだと分かってくれ」という自己正当化のために使われている。
ここ数年の選挙では辺野古基地反対派の敗北が続くが、それで沖縄の意志が変わったとするのも本土の傲慢である。既に25年を超える反対を続け、人々は疲弊している。容認と反対で集落が分断されて話もまともにできない状況が続き、日本本土からは建設強硬の圧力か、でなくとも無関心の風が冷たく吹きつける。
どれだけ反対しても国は容赦なく工事を続け、美しいエメラルドグリーンの海は目の前で埋め立てられていく。基地を受け入れれば、日本政府から多額の米軍再編交付金が入る。この状況で、反対の意志を表明しながら25年過ごすことだけでも大変なことである。それでも2019年の県民投票では2割弱の賛成に対し、7割強が辺野古埋め立てに反対の意志を示した。
建議書を渡して議論に加わることすらかなわなかった沖縄。今の私たち日本本土の沖縄に対する姿勢は、50年前と何か変わったのだろうか。
さるた・さよ
1977年東京都生まれ愛知県育ち。日本と米ニューヨーク州で弁護士。政策提言を行う新外交イニシアティブ(ND)では事務局長を経て2018年から代表。著書に「自発的対米従属」ほか。